「お金に悩まない未来を、新しい常識で」代表 堀井が語るスマートバンクの挑戦

―― まずはじめに、スマートバンクはどのような会社ですか?
堀井: スマートバンクは2019年に創業したフィンテック企業です。現在はコンシューマー(一般生活者)向けのAI家計簿アプリ「ワンバンク」を提供しています。「お金に悩まない未来を、新しい常識で」をミッションとして掲げ、お金に関するさまざまな課題を解決するためにプロダクト作りをしています。

―― 家計簿は古くからあり、同様のプロダクトを作ってきたプレイヤーもいたかと思います。その状況で、なぜ家計簿アプリに挑戦しているのですか?
堀井: 従来の紙の家計簿や家計簿アプリは、細かく家計管理できる層やマネーリテラシーの高い層の方にむけたものでした。現在、日本には「貯蓄ゼロ世帯」が約3000万世帯もあるというデータもあり、毎月の生活費をどうにかしたいような層もボリュームゾーンとして存在します。そのような人々にとっては従来の家計簿アプリはフィットしていないと考えました。
実際、リサーチをすると今でも生活費を現金を小分けにしてやりくりするアナログな方法を取っている方もいます。ユーザーが「不合理な代替手段」をとっていることにこそ、市場にいる顧客の「課題」が潜んでいます。従来の家計簿アプリでは解決できていない家計管理の課題を解決しようとこの領域に挑戦しています。
―― どういった時にその課題を感じたのですか?
堀井: 創業前にユーザーリサーチをするなかで、生活費をうまくコントロールできないため、現金で管理している方と出会いました。給料から生活費を現金で抜き出し、用途別に封筒に小分けにして保管することで「今月の生活費はこの金額内でおさめる」ということをアナログに管理されていたんです。仮にこういう人たちが既存の家計簿アプリを使ったとしても問題は解決されない。彼らは「お金の見える化」をしたいのではなく、「生活費をこの金額内でおさめたい」ということが本質的な課題であるというということに気付きました。
―― なるほど。そういった課題を解決する時に参考にしたモデルはありますか?
堀井: 海外、特にイギリスのスタートアップを参考にしました。イギリスには「チャレンジャーバンク」と呼ばれる銀行業のスタートアップがあり、先ほどのような問題を解決していました。イギリスの若年層はメガバンクを使わずに、チャレンジャーバンクをメイン口座にしてるという人も多いです。
チャレンジャーバンクのプロダクトはUIがシンプルで、デビットカードが即日発行され、残高をリアルタイムに確認でき、プッシュ通知も来る。そういった設計が若年層が手に取る理由になっていたのではないかと思います。
また、給料はメガバンクで受け取るが、生活費はチャレンジャーバンクに移している人もかなりいました。デビットカードで生活費を決済し、アプリで確認することで使いすぎを防ぎ、家計を管理していたのです。メガバンクでは解決できない問題をチャレンジャーバンクが解決していることを知りモデルケースのひとつとしています。
―― 既存の家計簿アプリは情報を集約するモデルですが、ワンバンクは何が違うのですか?
堀井: ワンバンクが発行するチャージ式のプリペイドカードを起点に、キャッシュレス決済をしながら家計管理ができる点です。このカードはリローダブルプリペイドカードと呼ばれ、繰り返しお金をチャージして使えるカードになっています。生活費用のお財布としてワンバンクカードを使ってもらうことで自動的に支出の情報が蓄積され、かんたんに家計を管理できます。
―― 決済と一体化しているということろが強みということですね。
堀井: はい。プリペイドカード決済の事業はユーザーさんからお金を預かって決済に使えるようにするため「資金移動業」の免許を取得する必要があります。国内で80社ぐらいしか持っていない免許で、取得には2年くらいかかりました。この免許があるからこそ決済と家計簿を組み合わせたプロダクトを作れたように、これからも免許によってできることを発明をしていくことが重要であると考えています。
―― 「発明」とのことでしたが、その事例・プロダクトを教えていただけますか?
堀井: カード決済と家計簿の組み合わせも発明のひとつですが、他にはカードにバリエーションをもたせた点も発明です。自分一人が使う「マイカード」をベースに、そこからの応用で、家計を共にしているパートナーと2枚のカードで共同管理できる「ペアカード」、お子さんに持たせて子どもの決済と支出管理に使える「ジュニアカード」の3種類があります。目的やライフスタイルに合わせてカードを発行して使えるようにする、というところも既存のプロダクトでは難しかったものの1つだと思っています。
―― そうしたプロダクト作りの中で、生成AIをどう位置づけていますか?
堀井: プロダクトを作る、つまり問題解決をすることは基本的に何かと何かの組み合わせです。AIと何を組み合わせたらうまく問題解決ができるのかを第一に考えるようにしています。AIで何かを作ったり、モデル自体をチューニングしたりするためにはデータが重要なため、ユーザーさんの支出データをワンバンクに預けてもらう必要があります。そのデータに対してAIが伴走する形で、複雑だったり、時間や手間をかけないと難しかったワークフローが効率的に解決できるようになり、より便利なプロダクトを作れると良いなと思います。コンシューマー向けプロダクトの一つがいわゆるAIエージェントになるのではないでしょうか。
―― プロダクトに生成AIを組み込む中で、フィンテックに固有の難しさはありますか?
堀井: 人によってお金に対する感覚や考え方が違うため、パーソナライゼーションは必須であると考えています。利用者が求めているレベル感に応じた体験であったり回答をいかに提供できるかが難しい点です。
また、金融領域だとハルシネーションが許容されにくいので、誤りを出にくくするようなガードレールの整備であったり、説明可能性、検証可能性といったところを含めた設計が必要になると思います。
あとはなんでもかんでもAIを入れていくのではなく、プロダクト全体を見た問に「ここにはAI」「ここにはAIではない解法」と見極めていくことも重要です。
―― プロダクトにAIを応用するにあたり、現状見えているテーマはありますか。
堀井:いずれ、家計のイベント予測はできるのではないかと思っています。予想される大きな支出のフォーキャストを出したり、将来的に発生するライフイベントに対して「これくらいのお金が必要になりますよ」とアドバイスするなど
あとは、現状のプロダクトにも組み込まれていますが、レシートやスクリーンショットのOCRの性能を上げたり、LLMによる情報抽出の性能を上げたりというものもあると思います。加えて重要になるのは、個人に寄り添った形で支出行動の分析をした上で便利な示唆を与えたり、提案をしたり、何かの行動を代行したりといったエージェントのようなものも必要であると考えています。
日本国内ではtoCのアプリでAIを前面に押し出しているサービスをあまり見かけないのでもっとやっていかなければならないと思います。10年後を考えた時、主要な金融機関に何らかのAIが乗っていないというのは考えられないので、今からどんどんチャレンジして積極的にプロダクトへ組み込んでいくべきだと確信しています。ただ、フィンテックはAIの誤回答に厳しい分野なので慎重に進める部分も必要になります。
―― プロダクト作りの楽しさのようなものはどこにありますか?
堀井: プロダクトが世に出て実際にユーザーの課題を解決できるところは楽しさの一つです。ただ、自分一人でやってると大きな成果を生むことはできないので、チームで成し遂げるところがやはり一番の醍醐味かなと思います。そうして課題を見つけ出し、解決するためのプロダクトを作れる・発明できる人が増えるとすごく嬉しいなと。
―― チームワークを重視されているように感じました。研究室に配属されている学生さんや研究者は、結構自分1人で何かを立ち上げていることも結構多いと思うのですが、チームワークの良さのようなものを教えていただけますか。
堀井: そもそも自分一人でできることには限界があります。スマートバンクは課題を見つけて、それを解決するプロダクトを作るスタンスの会社ですが、ユーザーのインサイトも捉えられて、デザインもできて、マーケティングもできて、コードも書けて、みたいなスーパーマンはいないじゃないですか。チームでうまく力を発揮することで、今まで解決されてこなかった世の中の課題を打ち壊すような製品を生み出すことができます。チームで事を成すことが今のスマートバンクでは大前提です。

―― チームに係る話題ですが、どういう人にスマートバンクに来てもらいたいですか?
何か特定のイシューをプロダクトで解決しようというスタンスが強い会社なので、自分でそういうものを生み出したい気持ちがある人にはぜひ来ていただきたいです。
一昔前と違って、インターネットの分野で一人で問題解決できるような領域はもう少ないので、大きなインパクトを生み出したかったら良いチームで、良いドメインに張って、それなりに資金のあるところにトライしていく必要があると思っていて、今のスマートバンクはここを満足している良い場所だと思います。
―― 最後に、これからチャレンジしたいけれどまだチャレンジできていない人に対して一言お願いします。
自分自身を含め「何か」を変えるには、自分でものを作って世の中に出すという手段以外は無いんじゃないかと思います。今いる組織でやっても良いですし、自分一人で週末に何か作るでも良い。とにかく、何かを作って出すということをやってみてほしいです。超くだらないものでも良いから、世の中に公開して、誰かに使ってもらって、自分以外の存在に何か影響を及ぼすものを作れば何かが変わっていくのだと信じています。



































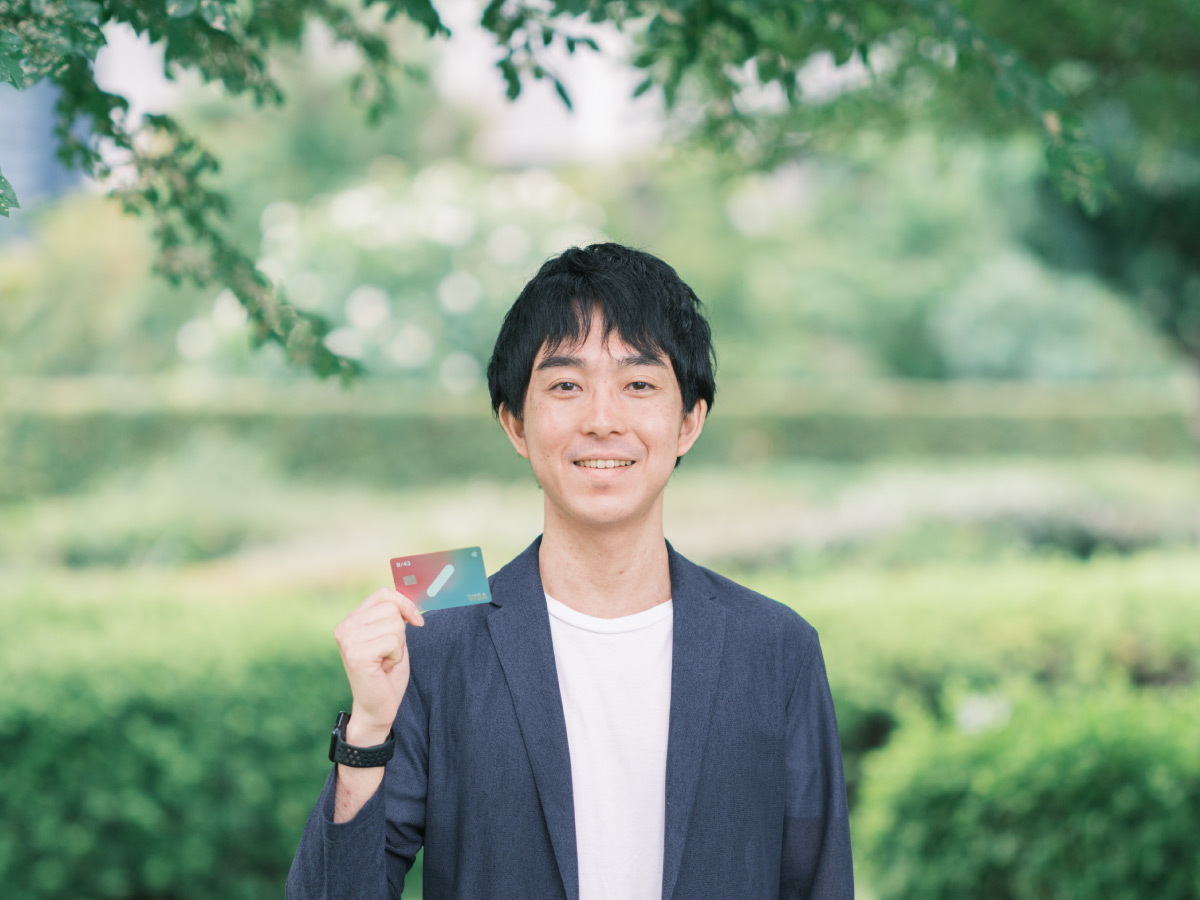



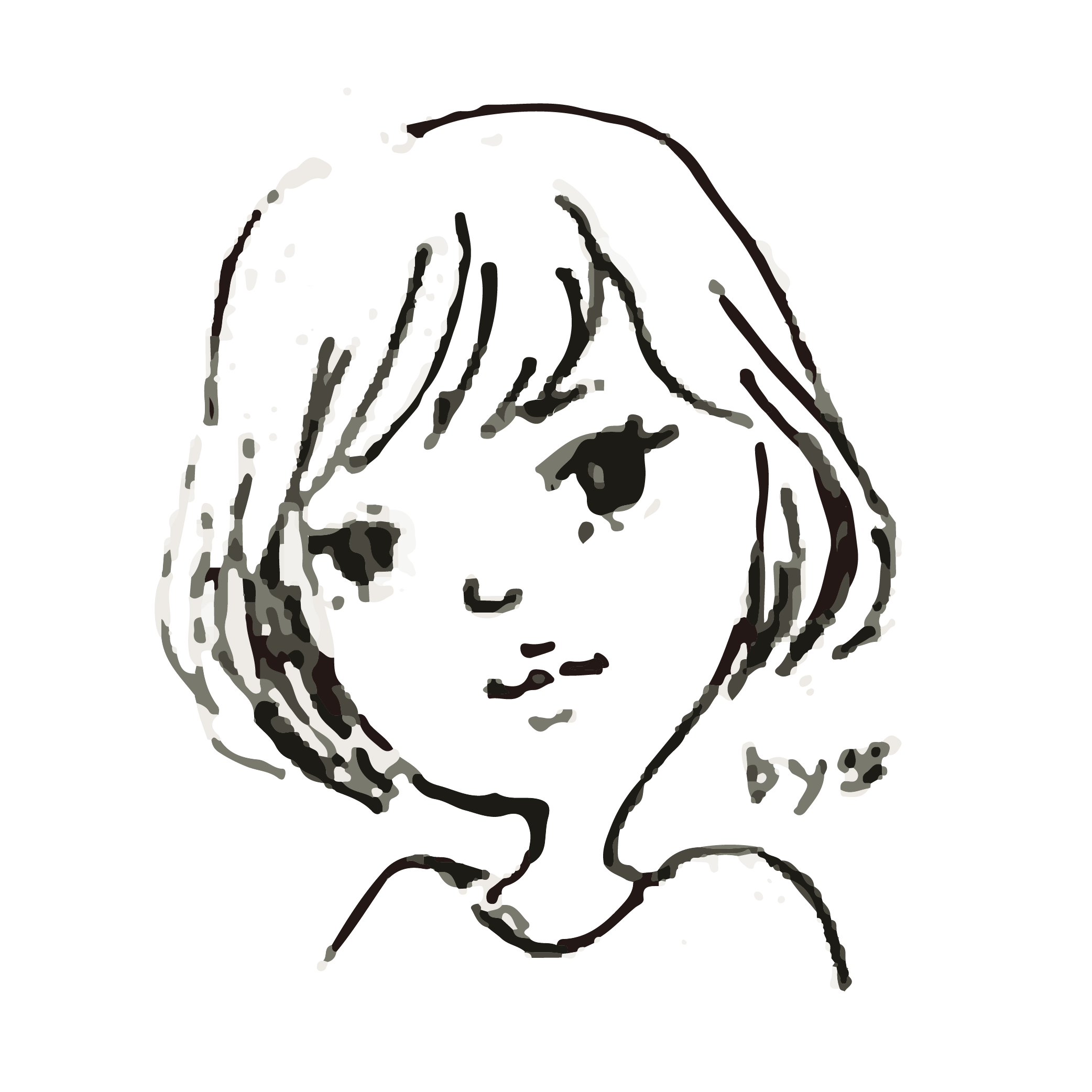



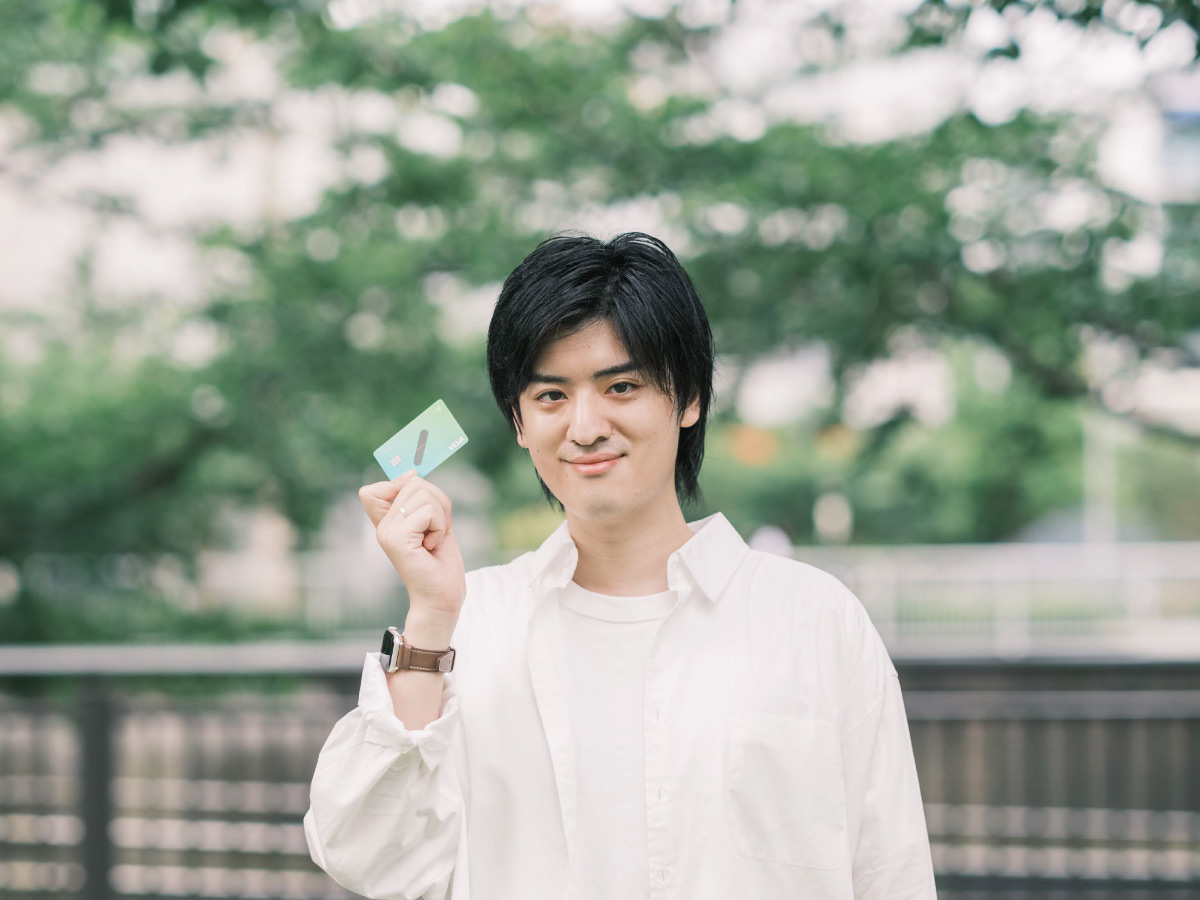






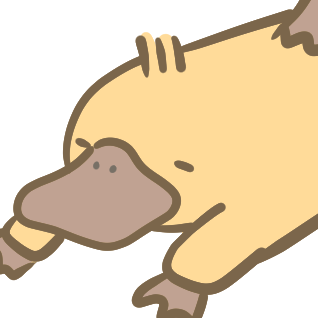
.JPG)





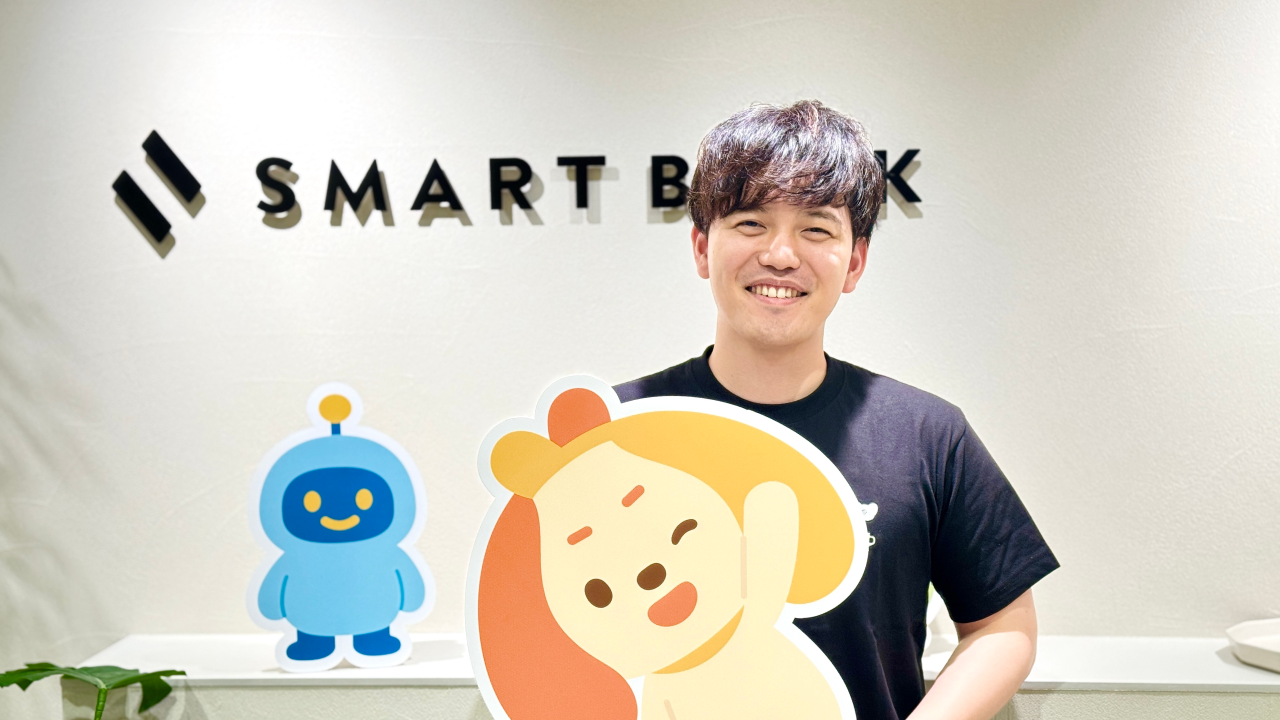
-(1).jpg)

-(1).jpg)






-(1).jpg)







